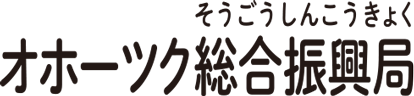| 腸管出血性大腸菌 (O157、O26等) に注意しましょう! |
|
腸管出血性大腸菌感染症 (O157,O26等)とは 腸管出血性大腸菌は大腸菌の仲間です。大腸菌は、家畜や人の腸内にも存在し、そのほとんどは害がありません。 しかし、大腸菌のうちのいくつかの種類が、人に下痢などの消化器症状を起こすことがあり、それを病原大腸菌と呼んでいます。なお、病原大腸菌の中には、毒素を産生し、出血を伴う腸炎や溶血性尿毒症症候群(HUS)を起こす腸管出血性大腸菌と呼ばれるものがあります。 |
 |
|
原因となる病原体 病気を起こすといわれている大腸菌は、約170種類ありますが、腸管出血性大腸菌感染症を起こすのは、O157、O26、O111などの種類です。重症化するものの多くは、O157です。 |
|
|
感染経路 菌に汚染された食品や、患者の便で汚染されたものに触れた手を介して起こる経口感染です。(話をしたり、くしゃみ、汗などでは感染しません) |
|
|
症状 感染後3~8日の潜伏期間の後、腹痛や水様性の下痢を起こします。後に出血性の下痢となることもあります。 まれに下痢などの初発症状の数日から2週間以内に、溶血性尿毒症症候群(HUS)や脳症などの重症合併症を発症することがあるので、特に抵抗力の弱い子どもや高齢者の方々は、注意が必要です。 HUSを発症し、急性腎不全などを生じた場合、死に至ることもあります。 |
|
|
発生時期 一年を通してみられますが、5月~10月の夏から秋に多く発生します。 紋別保健所管内の発生状況(北海道感染症情報センター) |
|
|
発生を防止するために 各家庭や食品関係施設では、次の事項に留意してください。 ○調理前や食事の前は、せっけんで手をよく洗いましょう。(消毒効果のあるものがよい。) ○加熱して調理する食品は、中まで火がとおるように十分に加熱しましょう。 ○目安は、食品の中心部の温度が75℃、1分間以上です。 ○調理された食品は、室温で長く放置せず、早めに食べましょう。 ○残った料理で、時間が経ったものや、少しでも危ないと思うものは、思い切って捨てましょう。 ○会食の席等で提供された食事の持ち帰りはやめましょう。 ○レバー等の食肉を生で食べることは控えるとともに、加熱不十分な食肉(牛タタキ等)を乳幼児やお年寄りに食べさせないようにしましょう。 |
|
|
<下痢等がある場合には次のことに注意しましょう> ○すぐに医師の診断を受けましょう。 ○便に汚染されたものに触れた手を介して感染しますので、石鹸を使い流水でしっかり手洗いしましょう。 ○タオルの共用は避けましょう。 ○入浴をする場合は、シャワーのみにするか最後に入浴するなどしましょう。 ○家庭用ビニールプールで水浴びをする場合、他の幼児とは一緒に入らないようにしましょう。 ○便に汚染された衣服などは、煮沸や薬剤で消毒したうえで、家族のものとは別に洗濯して天日で充分に乾かしてください。 |
|
|
■学校保健安全法での取り扱い 腸管出血性大腸菌感染症は、学校における予防すべき第三種の感染症に指定されており、有症状者の場合には、医師によって感染のおそれがないと認められるまで出席停止となっています。無症状病原体保有者の場合には出席停止の必要はなく、手洗いの励行等の一般的な予防方法の励行で二次感染は防止できるとされています。 |
|
|
◆腸管出血性大腸菌の情報のリンク先 腸管出血性大腸菌Q&A(厚生労働省) 一次、二次医療機関のための腸管出血性大腸菌(O157等)感染症治療の手引き(改訂版)(厚生労働省)
|
|