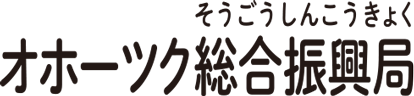私たちの住んでいる北海道には、エキノコックス症という、他の地方ではあまり見られない病気があります。この病気は、エキノコックスという寄生虫が主に肝臓に寄生しておこる病気で、道内では毎年10名~20名程度の患者が見つかっています。 |
||||||||||
| ○エキノコックス症とは | ||||||||||
寄生虫の一種です。単包性と多包性の2種類があり、北海道のものは、多包性のエキノコックスです。成虫(親虫)と幼虫(子虫)がいますが、成虫は主としてキツネに、幼虫は野ネズミ寄生しています。 成虫は卵をつくりますが、その卵が何らかの機会にヒトの口の中に入ると、腸で卵から幼虫となり、主に肝臓に寄生し、エキノコックス症と言う病気を引き起こします。 正しい知識があれば、感染を予防することができます。 |
||||||||||
| ○どのように人に感染するのですか | ||||||||||
エキノコックスの卵(0.03mmの球状で肉眼では見えません)が口に入ってしまった場合に感染することがあります。 エキノコックスが寄生したキツネやそのフンに直接さわったり、フンに汚染された山菜や沢水を口にすると感染の危険があります。 人から人、ブタや野ネズミから人に直接感染することはありません。 |
||||||||||
| ○寄生のリサイクル | ||||||||||
エキノコックスは、自然界においては、主にキツネと野ネズミに寄生しています。成虫はキツネの腸に寄生して卵をうみ、その卵がフンと一緒に排泄され、野ネズミが木の芽等と一緒にこの卵を食べると、野ネズミの体の中で卵がかえって幼虫となり、肝臓に寄生します。この幼虫が寄生している野ネズミをキツネが食べると、キツネの腸の中で幼虫が成虫になります。 このように、エキノコックスは、通常、キツネと野ネズミの間の「食べる」と「食べられる」という関係の中で生きています。 また、犬もキツネと同様に、エキノコックスに感染した野ネズミを食べることにより、エキノコックスの成虫が寄生します。 |
||||||||||
| ○エキノコックス症ってどんな病気 | ||||||||||
エキノコックスが主に肝臓に寄生しておこる病気です。人の体の中では、幼虫のまま肝臓の中で少しずつ大きくなっていきます。エキノコックスが寄生してもすぐには自覚症状がなく数年から十数年の潜伏期があり、肝機能障害等の症状が現れますが、普通の生活には特に支障がないため、自覚症状が出る頃には病気が悪化している可能性がありますので、健康診断で早めに発見することが大切です。 |
||||||||||
|
||||||||||
| ○予防する方法は | ||||||||||
| エキノコックス症の予防方法は、エキノコックスの卵が口に入らないようにすることが第一です。そのためには、次のことに注意しましょう。 | ||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
| ○検診はどこでやっていますか | ||||||||||
北海道内では、1次検診は市町村が行っています。その結果感染の可能性があった場合は、北海道が行っている2次検診を受けていただくことになります。1次検診は市町村で計画的に行われています。道内での生活が5年以上で検針を受けたことがない方、5年以上検針を受けていない方、キツネに触れた方、野ネズミを補食した犬を飼っている方は積極的に受信してください。道内の方で1次検診を希望される方は、お住まいの市町村にご相談下さい。 |
||||||||||